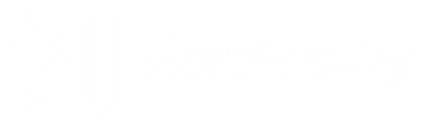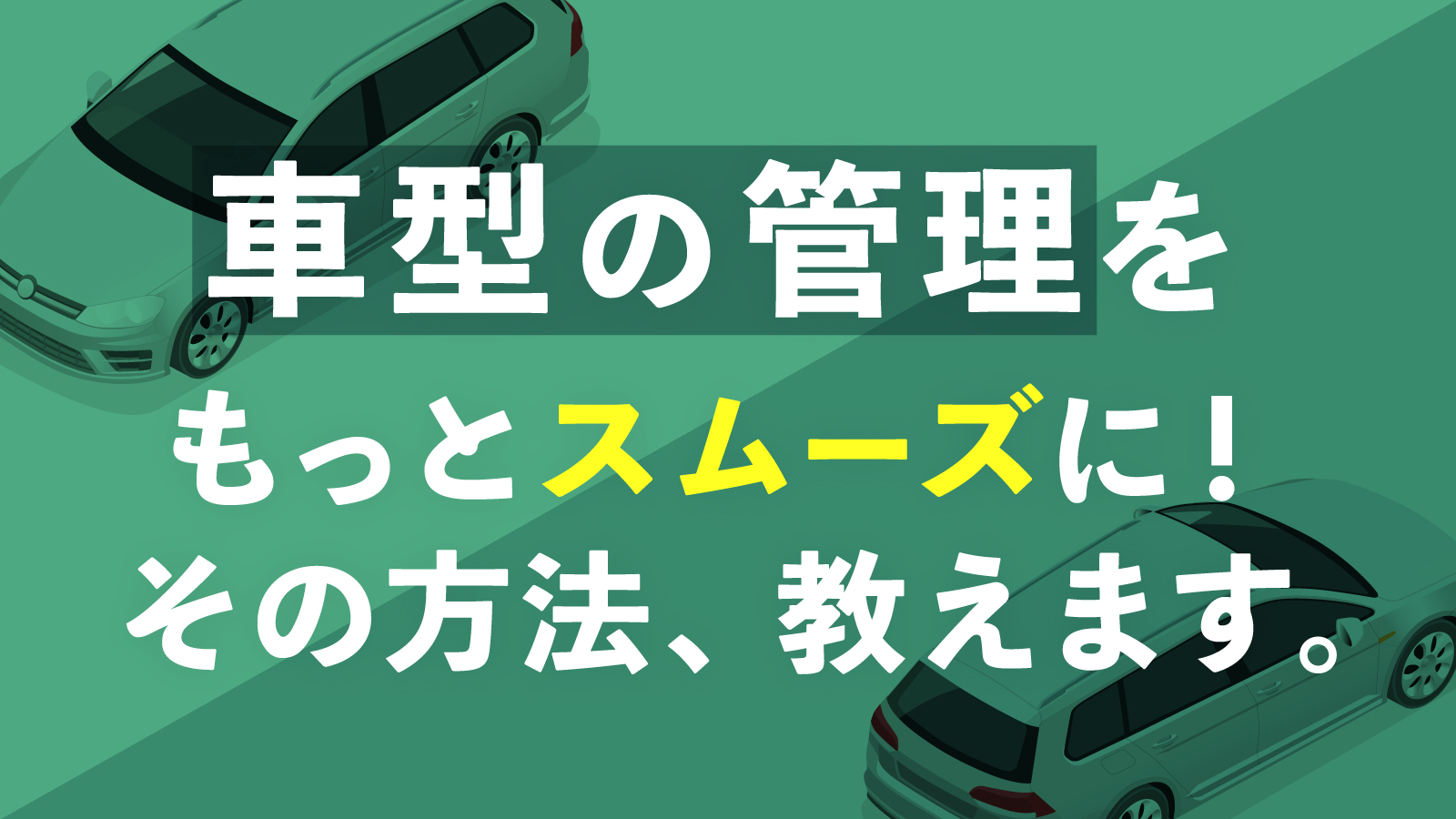『ベストカー』によると、日本では毎年10〜20種もの新車種が新規に販売されていますが、1台の車は約3万もの部品で成り立っています。自動車、自動車部品を製造する企業は1つ1つの部品に関する膨大なデータを細かく管理しています。データを管理する単位は様々ですが、その中において「車型(しゃけい・しゃがた)」は、その情報の上位をくくる、管理上重要なデータです。この記事では、自動車部品設計製造の車型管理における課題と、車型管理を効率的に行う方法についてご紹介していきます。
自動車製造の「車型」とは
日常的に車種・車名といった用語を耳にすることがあると思いますが、これらと「車型」はいったい何が違うのでしょうか。この章では、「車型」の意味と役割について解説していきます。
車種・車名・車型の違い
まず車種とは、文字通り車の種類のことで、主に用途やボディタイプで車種が分けられます。
例えば、普通乗用車・小型乗用車・小型貨物車・二輪車・営業用乗用車(タクシー)・営業用バス・自家用普通貨物車・営業用普通貨物車・ダンプ・特殊用途自動車(救急車、消防車など)といったものが、用途よって分類された車種です。
また、軽自動車やコンパクトカー、ミニバン、SUV、セダン、スポーツ、ステーションワゴン、ワンボックスといったものが、ボディタイプ(車のサイズやボンネットの有無など)によって分類された車種です。
次に車名とは、車のメーカーが名付けた車ごとの固有の名前を指します。
そのうえで車型とは、上記のいずれとも異なる車の開発単位ごとに割り当てられているコードネームで、自動車の製造業において使用されています。車名が同じでも、商品改良が行われたり、特別仕様車が販売されていたりすると、それぞれに異なる車型が割り当てられます。
自動車部品業界の製造現場で起こる課題
自動車部品の製造は、営業・設計開発・生産技術・生産管理・製造・設備保全など、さまざまな部門が連携して行っています。海外の事業部や工場とやりとりを行うことも一般的であり、多様な職種・部署が多様なデータを扱うため、情報の管理・活用においてさまざまな課題が発生します。
車型の変更への対応
新車型の立ち上げやモデルチェンジを行う時、車型を元に情報管理を行います。これは、企画段階から量産に至るまで、設計工程・生産準備工程を通じて共通です。設計仕様の変更や日程の変更、ほか様々な変更もふくめ車型を中心に情報を集約しながら、より良いクルマが作られていきます。
設計着手後も、さまざまに車型そのものの変更も実施されます。車型には部品の情報が紐づいているため、変更があれば、関連する各部署へのすみやかな伝達が必要です。
その際に、もし全部署に紙書面を送付したりしていたのでは、伝達に時間がかかるのみならず、最新情報の取り違え等も起きうることになります。そのような誤りが無いよう、確認もしなければなりません。エクセルやワードなどで管理している場合も同じです。それぞれの担当者が更新する必要がありますが、連絡や確認が漏れてしまうことにつながり、どの車型情報、それにひもづく技術情報が最新のものか、わからなくなってしまうことがあります。
大日程に合わせたスケジュール管理
車型には、メーカー指定の車型日程(大日程)が設定されており、それに合わせて設計した部品単位で日程を管理していきます。車型日程が変更されると、それに伴い、車型を構成するあらゆる部品の日程に変更が生じます。これらを各部署で調整し、変更された車型日程に統合していくのです。
各部署によって人材確保や材料の調達などの事情が絡み合うため、日程の変更はかなりの調整を伴います。一方で、車型の大日程はしばしば変更されるので、そのたびに各部品単位で日程の見直しが求められます。せっかく日程を調整してもすぐに変更され、負担に感じている部署の方が多い要因のひとつと言えます。
原価高騰による価格変動
日程とならぶ重要な管理項目に、車型の開発コスト・製造コストの管理があります。自動車の部品は日本国内で全てが完結することはおよそなく、それぞれの原価は、世界情勢によって常に価格変動が起きます。コロナ禍では世界中の都市がロックダウンされ、工場が稼働できない事態となりました。ロシアによるウクライナ侵攻では、資材の価格高騰や原油の価格高騰が起こっています。また、円安の影響もあり、原価の低減・調整は常に製造業における課題となっているのは周知の通りです。
部品1つでも原価が変化すれば、それは車型全体の原価に影響をおよぼします。そのため、原価の調整・計算は常に柔軟に行えることが大切です。
新技術への対応
ICTの進化や環境問題への意識の高まりなどから、自動車業界ではEV(電気自動車)やFCV(燃料電池車)など次世代自動車が台頭し始めています。また、経済的余裕がない・車に憧れを感じないなど若者の車離れが進んでおり、今後も車離れは進んでいくとの予測もあります。カーシェアリングなど車を所有せずにシェアするという、新しい価値観も広まってきているようです。
例えばこういった変化にも対応すべく、既存の管理・発想からの変革が求められています。プロダクトに対する変革、設計・製造に対する管理の変革、ともに必要といえるでしょう。
「ものづくリンク」の車型管理
車型管理の課題を解決するためには、車型情報をその他の技術情報・生産準備情報と一元管理していくことが有効です。JSOLが展開する「ものづくリンク」は、車型をPLMシステムとして集約し、変更にも即座に対応・部署を超えての共有が可能になります。
我々JSOLはNTTデータと日本総合研究所のグループ企業であり、製造業を深く理解したノウハウと、IT・システム開発に精通した高い技術力で、業界課題を解決するソリューションを提供しています。
車型を一元管理
「ものづくリンク」では、部品表を中心に、図面をはじめとする技術情報、生産準備に関する情報、日程情報、原価情報などを一括管理することが可能で、これを車型情報が束ねます。
具体的には、営業担当者が入力した受注情報、車型担当者が入力した日程表、生産技術が入力した部品情報、生産準備が入力した設備情報などあらゆるデータが部品表を中心に紐づいていくため、詳細の日程を車型担当者しか把握していなかったり、エクセルデータやファイルによって情報が行き違ったりすることがありません。
車型の変遷情報も統合することで、全員が常に同じ情報・最新の情報を見て仕事をするからです。
車型を一元管理することで生まれるメリット
車型を一元管理できれば、日程の変更が生じた時も、すぐに各部署に共有・調整することが可能です。車型から情報をひもとくことでいつでも最新の情報を、どの部署のメンバーでも問い合わせなく確認できるのです。そうすることで、メールや電話で都度担当者に問い合わせを行い、返事を待つ時間がなくなるため、業務のスピードをあげることができます。誰がどの車型の情報を持っているかを探す負担もなくなります。
こうして、新たな製品開発や品質向上への注力を実現します。
まとめ
車型変更によって生じるさまざまな業務の課題を、「ものづくリンク」で解決することができます。車型の管理だけでなく、生産準備における情報連携の強化、業務の効率化や、日程の管理も「ものづくリンク」で完結することが可能です。
自動車業界・自動車部品業界では、豊田鉃工株式会社、フタバ産業株式会社、株式会社協豊製作所、などで「ものづくリンク」が導入されています。車型日程表・生産準備日程表を全員で共有することで、今やるべき業務の明確化が実現され、業務改革の実行につながっているのです。
多言語対応やドラッグ&ドロップなどの共通部品と、必要な業務モジュールだけをカスタマイズしてシステム構築していくため、無駄なく、使いやすいシステムです。「ものづくリンク」はエクセルのような使い慣れた操作感が特徴で、Webブラウザにも対応しており、使えない社員がいないようサポートしていきます。
ものづくリンクで時代の変化に対応し、競合と差別化していく車型管理を叶えませんか?