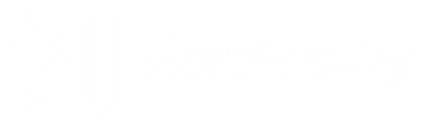日本国内でものづくりに携わる製造業においても、デジタル技術を活用しDXを推進する企業が増えてきました。その中でも、注目を集めているのが製品ライフサイクル管理を行うPLMというシステムです。
PLMは製造業の業務効率化や製品品質の向上を実現し、企業の収益を最大化することを目的とした取り組みのことを指します。今回の記事ではPLMシステムの概要や機能、もたらされるメリットなどに関して詳しく解説します。ぜひ、参考にしてください。
PLMとは
PLM(Product Lifecycle Management)とは、製品のライフサイクル管理のことです。1つのシステムのみで、製品の企画・設計・生産・販売・廃棄、もしくはリサイクルまでを踏まえた各プロセスにおける情報管理が可能になります。
PLMは収益の最大化を目的とした取り組みであり、製造業において重視されているQCD向上が実現できるとして期待が高まっているものです。自動車産業や電機産業にはじまり、航空・宇宙産業、最近ではアパレル業界など幅広い分野で導入が進んでいます。
PLMが求められる背景
PLMが求められるようになった背景には、QCDの追求や昨今の市場環境、社会情勢の変化などが挙げられるでしょう。4つの背景について、詳しく解説します。
QCDの追求
QCDとは、Quality(品質)、Cost(価格)、Delivery(納期)の3つの頭文字を取って並べたものです。激しさを増す市場競争や社会情勢の変化に伴い、低コストかつ質の高い製品を、スピーディーに市場に出す重要性が高まっています。
製品開発における一連の工程を見定め、QDCの3つの要素のバランスを取りながら取り組みを進めていくことが重要になるでしょう。QDC向上を実現するために、重要な役割を担うのが、PLMなのです。
QCDの具体的な取り組みとしては、VA(価値分析)、VE(価値工学)を踏まえた設計の早期作り込みを行うことや、トレーサビリティの向上、全部門情報連携を介した検索時間の短縮などが挙げられます。
多様化する市場への対応
ユーザー嗜好やニーズの多様化など、市場環境は日々目まぐるしい変化を遂げています。このような近年多様化する市場に対応するため、PLMが求められるようになったのも理由の1つです。
これまで生産情報の管理や共有は、紙やエクセルを使用することで行われてきました。しかし、デジタル化が進む昨今の社会情勢では、IoTなどのIT技術を活用した情報のデジタル化を進めることがスムーズな情報共有に繋がると考えられています。
トレンドの変化などの市場変化などの情報を集約し、製品ライフサイクル管理全体を担えるPLMが必要とされているのです。
生産拠点のグローバル展開
グローバル化の波が押し寄せた2000年以降、低コスト生産が実現できることなどを理由として、日本の製造業は積極的に海外への進出を推し進めてきました。そこで、注目されたのがPLMです。
PLMを導入することで、生産だけではなく、設計や開発までを海外にシフトするなどのビジネス環境変化に対応が可能となります。それだけに留まらず、PLMは国際競争力向上にも寄与するでしょう。
コンプライアンス遵守
SDGsの考え方が広がる社会情勢の中で、製品の品質や安全性に対しての規制が厳しさを増しています。そのため、企業には柔軟かつ迅速な対応や、コンプライアンス重視のモノづくりが求められるようになりました。
PLMは製品を製造する上での全てのプロセスを総合的に管理できるため、製品の法的コンプライアンスの遵守に対してスムーズな対応が可能です。より安全性の高い製品を提供することが可能になるでしょう。
PLMの機能
PLMの機能は多岐に渡りますが、複数の機能を組み合わせて活用を行うことで業務効率化や競争力向上に繋がっていくでしょう。
今回は製造業における業務プロセスのつながりを指すエンジニアリングチェーンに注目して解説していきます。
CAD連携
CAD(Computer Aided Design)とは、従来手書きで行われていた設計作業についてコンピューターを利用することで効率化する機能のことです。2次元データを扱う2DCADと3次元データを扱う3DCADに分かれています。
CAD連携はPLMの中でも中核を担う重要な機能です。CADに登録されている部品構成や品目属性をPLMに連携することで、二重入力や誤入力を防ぐことができます。
製造業のDX推進においては、3DCAD活用がデジタルエンジニアリングの柱となっています。
設計変更管理
設計変更とは、製品の仕様変更のため、図面を書き換えることです。一般的には、製品を製造する過程における問題や課題を解決する場面で設計変更が行われますが、このような場合、企業の信用低下に繋がる可能性もあるため、迅速な対応が求められます。
PLMシステムを導入することで、設計変更の一連の流れを管理することができるため、適切な時期での設計変更の反映や設計変更漏れの防止に繋げることが可能になるでしょう。
部品表管理
部品表の管理は紙やエクセルで管理されている企業も多く、情報の二重入力や属人化など、多くの課題が残されています。PLMの部品表管理機能を活用することで、課題を解決し、業務効率化に繋げることが可能になるでしょう。
設計、製造部門の部品のみならず、調達・購買部門、納品後のメンテナンスに使用する資材にも対応しています。さまざまな部門の部品表をデータベース化することで、製品ライフサイクル全体での一貫した部品在庫管理が可能となるでしょう。
ドキュメント管理
製造業では、図面や技術関連の文書など数多くのドキュメントが存在します。適切なドキュメント管理が行われていない企業では、全社で共有すべきドキュメントも、各部署や各個人で管理しているケースが多く見受けられます。そのため、他部署で管理しているドキュメントを参照するには、その都度問い合わせを行う必要がありました。また、エクセルや紙で管理しているため、検索に時間がかかる問題も発生します。
PLMに登録することで、すべてのユーザーが同じ部品表や図面などのドキュメントをいつでもすぐに参照可能になります。ドキュメントを登録する際、品番等を紐づけて管理できるため、必要な情報の検索も容易になるでしょう。また、履歴管理機能もあるため、いつでも最新版のドキュメントを参照することが可能です。
3Dデジタルデータ
生産準備業務において、実機を使用した組立プロセス検討や作業指示書作成などは実機を使用した方法が一般的で、属人化や品質を均一に保てないなどの課題がありました。
3Dデジタルデータを活用することで、組立手順や用いる工具など、より詳しい製造情報が視覚的に把握することが可能になります。従来の方法での課題を解決できるだけでなく、製品開発の効率化や納期の短縮にも繋げることができるでしょう。
PLM導入のメリット
設計から廃棄までの業務プロセスについてPLMを導入しデジタル化することで、業務効率化や製品品質の向上、リードタイムの短縮やコスト削減に繋げることが可能になります。
PLMを導入することで得られるメリットについて、詳しく解説します。
業務効率化
従来、紙やエクセルを使用して行ってきた業務にPLMを導入してデジタル化すると、製品開発に携わる全ての部門の業務効率化が可能です。具体的には製造工程の見直しの作業時間や、製品の仕様変更に要する時間の短縮などが挙げられます。
各部門間での情報共有も容易に行えるようになり、各部門が保有している貴重な製品情報を会社全体で活用することが可能になるでしょう。これまで他部門との連携に要していた時間を、他の生産性を高める業務に割くことができるようになることもメリットの1つであるといえます。
品質向上
製品製造のライフサイクル全体で情報共有が可能なPLMは、品質の向上にも繋がるメリットがあります。各工程データを一括管理することで、製品の不具合の発見や不具合に対する修正を迅速に行うことが可能であるほか、各部門が連携することで効率的な品質検査にも繋がるでしょう。
現場担当者の負担を減らしつつ質の高い製品開発が可能であるため、多様化する顧客ニーズ対応への期待も高まっています。
リードタイムの短縮
PLMを導入することで、製品開発の流れを総合的に管理し、現在の進捗状況を即時に把握することが可能になります。担当者間での情報共有や、各製造プロセスの同時作業も容易になり、設計から販売までの所要時間であるリードタイムを短縮する効果も期待できるでしょう。
また、リードタイムを短縮することで市場投入時期を適切にコントロールすることも可能になります。
コスト削減
PLMを導入することで、製品開発段階で生じるさまざまなコストの削減を図ることが可能になります。業務効率化が促進されることでの人的コストの削減や、余剰在庫を避けることで金銭的コストの軽減効果も期待されるでしょう。
また、設計図面などのデータを一括管理することで、情報共有や利活用が容易になり、設計作業の無駄を省くことができるなど時間的なコストの削減にも有効です。
このようにPLMの機能を有効活用することで、さまざまなコスト削減に繋げることができます。結果として、企業の利益向上効果も期待できるでしょう。
PLMとPDMの違い
PLMと類似するシステムにPDM(Product Data Management)というものがあります。PDMは、CADデータや図面ドキュメントなどの設計データを一括管理して生産工程の効率化を図ることを目的とし1990年代に登場したシステムです。
PLMとPDMの大きな違いは、データ管理を行う対象範囲であるといえるでしょう。PLMは製品ライフサイクルで使用される全てのデータが対象であるのに対し、PDMは開発・設計段階で用いられるCADデータなどのドキュメントファイルが対象になります。
PLMとPDM、それぞれの定義はあるものの、厳密に決められているわけではありません。会社によっては、PLMとPDMの対象とは異なるシステムを提供している場合もあるため、導入の検討段階で仕様をしっかりと確認しておくことが重要になります。
まとめ
PLMは製品ライフサイクル全体の流れを把握し、業務効率化やコスト削減に有効なシステムです。製品の質を向上させるメリットもあり、多様化する顧客ニーズに対応することにより顧客満足度の向上や、企業価値を高めることにも繋がるでしょう。
日本国内の企業がDX推進を図る中、製造業においてもデジタル化を進めることが重要となります。利益の最大化はもちろん、企業競争力の向上に向けてPLMを有効活用してみてはいかがでしょうか。
JSOLが提供するPLMソリューションサービス『ものづくリンク』は、設計・開発、生産準備といったものづくりの過程において各部門で発生する図面や部品表、材料表や生産工程表といったさまざまな情報を「部品表」に統合し、全社レベルで共有できるPLMソリューションサービスです。業務のペーパーレス化を推進し、業務の効率化やデータの検索性アップを実現します。
PLMシステムの導入をご検討中なら、『ものづくリンク』を試してみませんか。