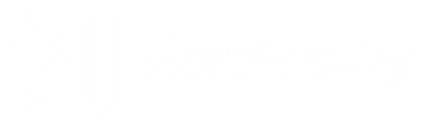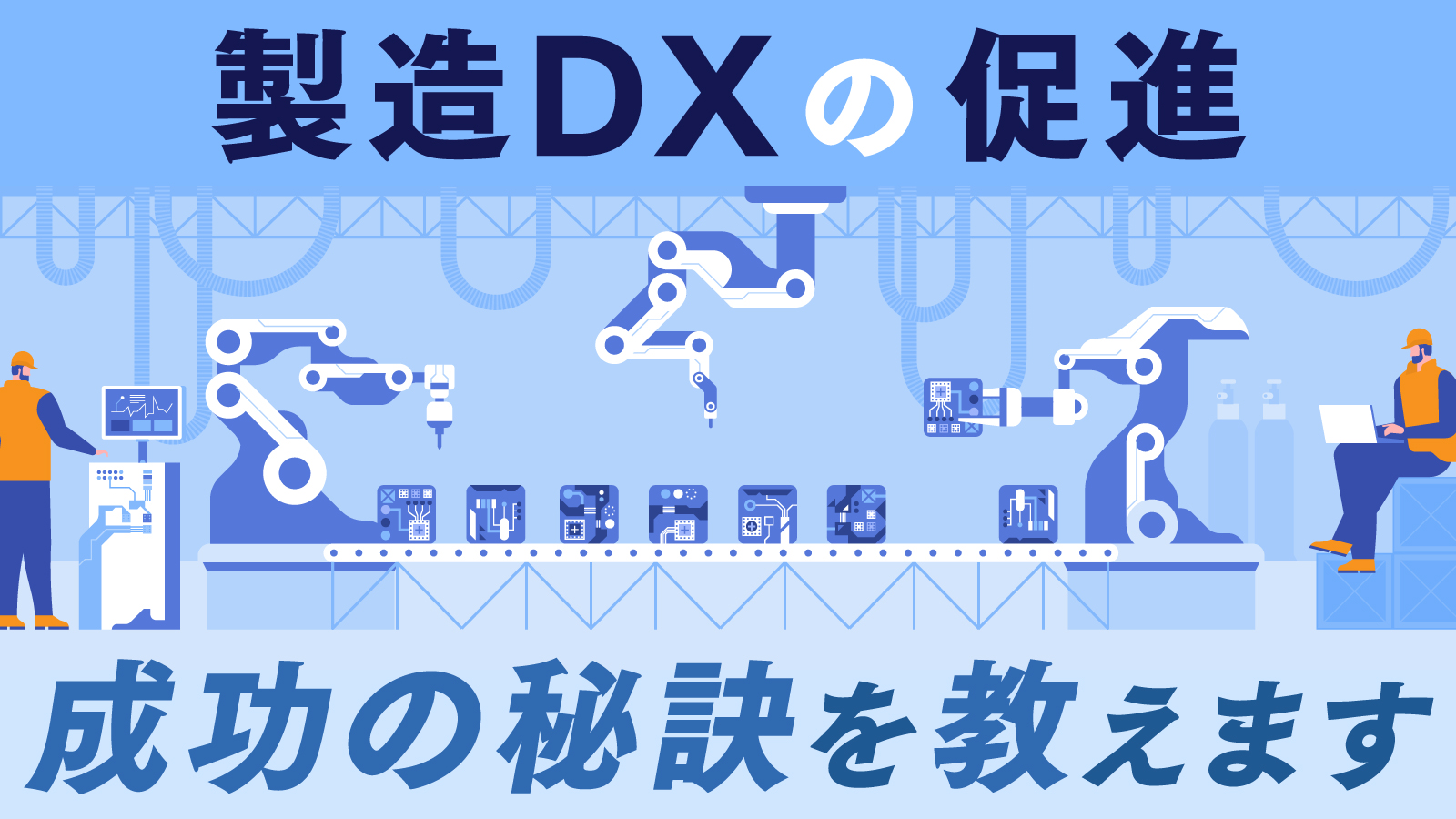経済産業省は国内企業の競争力を高めるためにDXを推進しています。製造業でもDXを進めることでさまざまなメリットが期待できますが、取り組む上での課題も多く、自社のDXがなかなか進まないと感じる企業も少なくないようです。
今回は、製造DXとはどのようなものかを詳しく解説し、成功の秘訣やシステム導入のポイントを紹介します。
製造DXとは
製造DXとは、製造業においてITを活用することで、企業を革新していく取り組みです。既存事業の生産性を高めるだけでなく、新たなビジネスモデルを生み出すことが可能になると期待されています。
具体的な製造DXとしては、自動化ツールや、AI、IoTなどの最新テクノロジーが話題になりがちですが、これから製造DXに取り組みたいという企業にはハードルが高いかもしれません。まずは業務の電子化やデータベース化といったスモールステップのデジタル化を図り、徐々にDXを進めていくとよいでしょう。
なぜ今製造DXが求められるのか
製造DXが求められる背景には、デジタル技術で変化した社会に対応していくことの必要性があります。製造業では特に、アナログな職人技術に頼っている企業も多く、デジタル化された社会の中で経営を維持できなくなる恐れがあるのです。
もちろん継承するべき職人技術もありますが、テクノロジーを導入できる工程やバックオフィス業務などの分野でDX化を進めれば、生産性や競争力を高められると期待されています。
また、製造DXの推進は業務効率化につながり、作業時間や人員、費用などに余裕が生まれるので、開発のような新しい挑戦につながる業務に注力できるようにもなるでしょう。製造DXで企業の革新を図ることは、デジタル社会で生き残る術として必要不可欠な取り組みになってきているのです。
経済産業省が製造DXを推進
経済産業省も製造DXを推進しています。製造業の各工程にデジタル技術を取り入れることで、データの利活用が促進され、画期的な革新が可能になると期待しているのです。
製造業の工程には、「エンジニアリングチェーン」と呼ばれる研究開発から生産などの連鎖と、「サプライチェーン」と呼ばれる受発注から販売・アフターサービスなどの連鎖があります。2つのチェーンを通して生産技術や製品に関するデータが流れ、結び付いたり付加価値を生み出したりするので、双方の連携は欠かせません。しかし国内の製造業企業の多くは、データ活用の分野で後れを見せているのが現状です。
AIを研究開発に導入する、顧客データの分析で販売予測をするなど、2つのチェーンに適切なデジタル技術を導入すれば、各工程でのデータ収集や管理が最適化されます。データ共有がしやすくなるため2つのチェーンに滑らかな連携が生まれるでしょう。
近年注目されている「サービタイゼーション」など、製品をサービスの一環という位置づけで扱うような新しいビジネスモデルの設計にも取り組みやすくなります。
製造DXにおける課題
製造DXの推進を図る企業は多いものの、取り組みが思うように進まないと感じている場合もあるようです。製造DXにおける課題を挙げて解決策を解説します。
情報が属人化している
DXの推進にあたっては、データを企業全体で共有することが重要です。まずは情報を見える化することで、課題点や改善点を発見することができ、適切なデジタル技術の導入を検討できるのです。
しかし現状は、情報が特定の従業員に集中した状態で処理されている場合が少なくありません。国内の製造業では、現場や職人を第一に考える風潮が強くあり、現場で優秀な人財を中心にして業務が展開されることが多いのが現状です。DXを進めるためには、現場での入念なヒアリングなどを通して情報を見える化し、属人化を解消していく必要があります。
製造業とDX双方に精通した人間が少ない
製造DXを進めるには、製造業とDXの双方の知識と技術を持った人財が必要です。しかし国内では、デジタルに強い人財がIT関連企業などに集中しているため、製造業の分野に強いDX人財は少なく、確保することが難しい状況です。
外部からDX人財を採用するのが難しい場合は、社内で育成を行うことが人財不足解消の方法になるでしょう。自社が求めるDX人財に必要な知識やスキルを、従業員が学習できる機会を整備します。研修などの教育プログラムを展開するほか、日常の業務でIT技術やDXプロジェクトに携われる環境を作ることも効果的です。
部署間の壁が高く、全社全体最適の重要性に対する理解が乏しい
部署によって製造DXへの意識が異なり、壁を感じている企業も多いようです。特に経営層が理想とする製造DX像と、現場が求める具体的な改善策にギャップがあるという場合が少なくありません。
現場で大きな問題を感じずに生産活動ができている場合は、従来からの方法を変更することに疑問を感じる従業員もいるでしょう。慣れないデジタル技術を導入するということに抵抗がある人も多いものです。経営層はDXで目指すビジョンや得られるメリットを明確にして伝えるとともに、現場の声のヒアリングや、定期的な進捗状況の共有を行い、DXに取り組むことへの理解を社内全体に広げるように工夫しましょう。
製造DXにより実現できること
製造DXに取り組むと現行の業務が改善されるだけではなく、企業風土やビジネスモデルを革新するような、事業の大きな変革を実現できます。たとえば車の製造業ならば、車の販売だけにとどまらず、新しいサービスを開発して移動ツールを売る事業へとスケールアップするというような挑戦です。製造DXによって実現できることを紹介します。
情報の見える化
情報の見える化が実現され、データを社内全体で有効活用できるようになるのは製造DXの大きなメリットです。デジタル技術を導入して製造DXに取り組むと、作業の属人化を解消することができるので、フィードバックが情報として残ります。
生産や設備の状況をデータ化して管理できるようになるため、トラブルの早期発見がしやすくなるほか、収集したデータの分析結果をさまざまな予測や開発に役立てることができるでしょう。
製品の品質向上
デジタル化を進める製造DXに取り組むと、各工程のデータ収集が行いやすくなります。フィードバックを情報として残す、データを分析するといった取り組みが容易になるため、製造上の課題や顧客のニーズが明らかになり、改善策の検討に有効活用できます。既存製品のブラッシュアップや新商品の開発が行いやすくなり、製品の品質向上につながるのです。
また、DXを活用して作業の属人化を解消できれば、特定の従業員に依存することなく安定した業務を行うことができるので、品質向上に貢献するでしょう。
業務効率化
デジタル技術を取り入れることで業務効率化が大幅に進みます。適切なITツールを導入すれば、現場の設備や事務作業などのさまざまな業務を自動化できるので、作業時間や人的コストを削減できるでしょう。
人財育成
製造DXのプロジェクトを全社で一丸となって進めれば、従業員がデジタル技術に触れる機会が増え、人財育成につながります。製造DXに詳しい人財は国内で不足している傾向にあるのが現状です。DX人財を社内で育成できれば、他社との差別化を図る活動も可能になり、今後の企業の成長に大きく影響するでしょう。
製造DXを成功させるポイント
製造DXを進めるためには社内外での連携や、明確なビジョンの制定が必要です。製造DXを成功させる4つのポイントを紹介します。
製造業とDX双方を理解しているサービスを利用する
デジタル技術の活用には専門知識が必要であるため、DXの推進は社外のサービスも有効活用しながら進めていきましょう。
利用するサービスを選定する際にポイントになるのは、製造業とDX双方への理解があるかどうかという点です。サービスを提供している会社の得意分野や、これまで行ってきたDX推進の実績を確認し、自社のDX推進を実現できるサービスを検討しましょう。
社内でのDXの必要性の理解
DXの推進は段階を踏んで計画的に行っていくものなので、社内全体の協力が必要です。経営層だけでなく全ての従業員に製造DXの必要性を理解してもらうことが、成功につながるポイントであると言えるでしょう。DX推進のメリットをわかりやすく説明し、意欲的に取り組める環境に整えることが重要です。
部門ごとの情報管理の整理
製造DXではデータを分析して改善や開発に役立てることで、企業の成長を促します。デジタル技術を用いるとさまざまなデータが簡単に得られるようになりますが、活用できないと意味がありません。必要な時にすぐに利用できるように適切に管理することが重要です。部門ごとに情報管理を整理しておきましょう。
数年後、企業としてどうなりたいかというビジョンの明確化
DX推進によって企業をどのように変革していきたいのか、ビジョンを明確にして取り組みましょう。便利そうであるからというような理由でデジタル機材を導入しても、業務の実態に合っておらず、コストや時間が無駄になってしまうことが少なくありません。
数年先まで考えて、目指すビジョンを明確にした上で必要な機材やサービスを検討し、社内全体で一丸となって取り組むことが必要です。
製造DXの成功事例
製造DXのビジョン制定や取り組みの方を検討する際には、他社の成功事例を参考にすると考えやすくなります。
また、製造DX推進にはソリューションなどのサービスを活用することも必要となりますが、提供会社によって得意分野が異なるため、過去の成功事例や実績を確認して選ぶとよいでしょう。製造DXの成功事例を挙げてご紹介します。
協豊製作所様
協豊製作所様は、自動車部品の生産や工場の運営サポートといった事業を展開されている企業です。長年使ってきた生産準備システムについて課題を感じて製造DXに取り組み、従業員の負担軽減やデータ管理の一元化を成功させました。
製造DXの推進にあたり、新しいシステムとしてJSOLの組立製造業向けPLMソリューション「ものづくリンク」を導入しています。生産準備に必要な情報が「ものづくリンク」に集約するため、担当者間の問い合わせを減らすことができ、大きな効果があったようです。
また、部品評価に基づいた原価の自動算出によって管理業務の負担が減り、大幅な期間短縮にも成功しています。情報共有が簡単になり、今やるべき作業もわかりやすくなりました。部署ごとの情報入力のタイミングなどを整備して業務改革も実行できたということです。
既存の管理システムなどに課題を感じている場合は、協豊製作所様の成功事例を参考にして製造DXに取り組んでみるとよいでしょう。
まとめ
社内の製造DXが成功すれば、企業を大きく革新していくことができます。どんな企業になりたいかというビジョンを明確にしたら、まずは業務の電子化やデータベース化のようなスモールステップの製造DXから進めていきましょう。
製造DXを効率的に取り組むためには、PLMソリューションサービスを利用することがおすすめです。中でも製造業とDXの双方に理解がある「ものづくリンク」のようなサービスを選ぶようにしましょう。
JSOLが提供するPLMソリューションサービス『ものづくリンク』は、設計・開発、生産準備といったものづくりの過程において各部門で発生する図面や部品表、材料表や生産工程表といったさまざまな情報を「部品表」に統合し、全社レベルで共有できるPLMソリューションサービスです。業務のペーパーレス化を推進し、業務の効率化やデータの検索性アップを実現します。
製造DXがうまく進められずお悩みなら、『ものづくリンク』にぜひご相談ください。