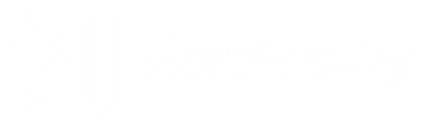電気・電子機器に内蔵されるカスタム製品の設計・開発から生産、販売までを一気通貫して行っているパワーサプライテクノロジー(以下、PST)。年間100品番にも上るカスタム製品を設計・開発しているが、グループ企業が共通で利用していた PLM(Product Lifecycle Management)パッケージではPSTの業務領域をカバーできず、いくつものシステムやツールを併用していた。それでも情報の共有、有効活用が難しかったことから、業務全体を一元的に管理できる新たなPLMシステムの構築に向けて検討を進めていくことに。その結果、選ばれたのがJSOLのPLMソリューション「ものづくリンク」であった。
課題
● カスタム製品の設計・開発には、膨大な図面、ドキュメントが発生し、多大な工数が必要。効率化には全ての製品情報を一元化のうえ共有することが必須だった
● これまでのPLMパッケージには設計・開発工程に必要な機能が不足。業務の全領域をカバーできるPLMパッケージへの刷新が求められていた
● 業務部門の要求に応えられる、使いやすいPLMを開発したかった
解決
● PLMソリューション「ものづくリンク」の導入
効果
● 全ての製品情報の一元管理に加え、最適な業務フローに合致したワークフローも併せて一元化することで、部門間の情報共有、連携もスムーズに
● 開発ステップごとの進捗、課題もスムーズに情報共有でき、業務の進行状況をリアルタイムに把握。作業者のスキル向上にも貢献
● ライセンスフリーのため、全従業員が同時にアクセスできるようになり、高い利活用を実現
● 稼働後も現場部門のさらなる改善要望を受け、継続して機能向上。さらなる業務効率化を推進

技術1部 高圧トランス設計課
課長 兼 技術管理課 課長
田畑 亘氏
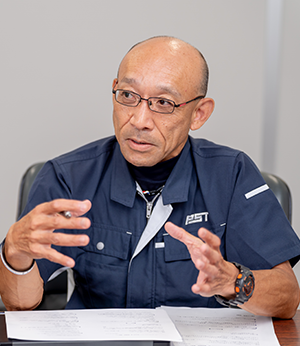
技術1部 技術管理課 係長
前川 元伸 氏

技術1部 技術管理課 主事
浅野 公洋 氏

技術1部 技術管理課
矢木 陽優 氏
機器の用途や顧客の要望に応じて、新製品を設計・開発
PSTは、幅広い業種に向けてスイッチング電源、高圧電源、高圧トランス、マグネットロールといったさまざまなカスタム製品を提供している。
PSTの特徴について、技術1部 高圧トランス設計課 課長 兼 技術管理課 課長の田畑亘氏は「当社は複合印刷機器や産業・環境機器などに内蔵されるカスタム製品を、年間で約100品番もの設計・開発をしています」と説明する。
同社にとって多種多様な製品を設計・開発する上で課題となっていたのがPLM(Product Lifecycle Management)の高度化だった。PLMとは、引合から設計・開発、試作、生産とつながる、ものづくりの工程全体を管理するシステムのこと。nms ホールディングスグループの一員であるPSTでは、元々グループ共通のPLMパッケージ製品を利用していたが、一口に組立製造業といっても製品特性などによって求めるPLMの姿はさまざまである。特に、PSTは多数の新製品を設計・開発するため、量産前の各工程の作業も膨大になる。
よりスムーズな設計・開発を目指し、PLMの一元化を検討
「従来のPLMは開発後の工程に強みを持つものでしたので、当社が求める設計、開発に関する機能が不足していました。そのため、いくつものシステムや表計算ソフトなどのツールも併用しながら機能を補填し、なんとか対応していたところです」(田畑氏)
技術1部 技術管理課 係長の前川元伸氏は当時の課題として「業務の一貫性が見えにくかった」ことを挙げる。量産に入る前には、複数の部門が引継、連携しながら業務を進めていく。営業部門が取引先からの引合を受け、技術部門が設計検討を進めつつ、併せて品質保証部門がその品質を検証するという形だ。いくつものシステム、ツールを使い分けていることで、業務の一貫性が保てず引継に非常に多くの手間・時間がかかってしまっていた。
また、取り扱う図面・ドキュメントの量も多く、要求仕様書や設計仕様書、評価レポートなどは一つの製品あたり合わせて数百に達するが、それも個別に管理している状態だった。ドキュメントが必要になったときには、その都度担当者に連絡を取り、最新版を入手しなければならなかった。
「業務全体を見通せるシステムがなかったので、引継の際には担当者の努力で乗り切っていたのが実情でした。抜け漏れがないように進めるには大きな労力がかかっていました」(前川氏)
また従来のPLMには同時利用数に制限があり、「使いたいときに使えない」ことも多く、一部の技術部門の利用のみにとどまっていたことも情報活用の妨げであった。
豊富なモジュールを備えたPLMソリューション「ものづくリンク」を導入
改善の必要性が高まっていたところに、従来のPLMのバージョンアップの連絡が届いた。これを機に「コストをかけて継続するより、業務形態にマッチした次世代のPLMへ刷新しよう」と動き出した。
技術1部 技術管理課の矢木陽優氏は「まず社内で理想のPLMの形を議論しました。私たちが求めていたのは、お客さまからの引合から設計・開発、量産へという業務全体を一元的に管理でき、ドキュメントも含めて一貫性を持って見渡せる仕組みでした」と語る。
そして2018年に声をかけたベンダーのひとつに、PLMソリューション「ものづくリンク」を提案したJSOLがあった。ものづくリンクは、部品表や図面、材料、工程表などを一元管理するPLMで、異なる部署が連携しながら設計、開発していくという業務の形に合致すると考えられた。基本的な機能をモジュールとして用意し、そのほかに必要なモジュールも組み合わせながら機能を追加、拡充してシステムを構築していくので、柔軟性と拡張性にも優れている。
またライセンスフリーなので、全員が同時にアクセスしても問題なく利用できる。それらを踏まえて、ものづくリンクの採用が決定した。

隔週での会議を繰り返し、現場の意見・要望を深く共有
より自社の事業形態にあったPLMを作り上げるため、各部門の担当者にも深く関わってもらうことにした。同様に、「最初のステップとしてJSOLにお願いしたのは、業務における現場の実情を知っていただくこと。大阪、名古屋にも拠点を持つJSOLは当社にも近く、何度も足を運んでいただき、各現場の担当者も交えた会議を隔週で行いました」(田畑氏)
積極的に現場を巻き込んだことで、「自分たちの業務を改善するシステムを、みんなで作り上げよう」という意識を生み出し、多くの意見を引き出せた。新たなPLMに移行した際も、現場にスムーズに浸透させることにつながったという。
技術1部 技術管理課 主事の浅野公洋氏は、「JSOLからは、より良いものを一緒に作ろうという強い熱意が伝わってきました。いろいろな業界、業種での知見・経験を踏まえて、新しい視点での提案もしてくれました」と、積極的な提案と姿勢を評価する。
そして2019年6月、ものづくリンクをベースにしたPLMが稼働した。
一元管理と業務の可視化で、部門間の連携がスムーズに。社員教育にも効果
新たなPLMは、引合内容登録、プロジェクト管理、ゲート管理、部品管理、部品表、図面・ドキュメント管理などの機能を持ち、営業から技術、調達、品質保証、製造へと連なる全ての製品情報を一元的に管理できるようになった。
「新しいPLMでは、正しく工程を完了しないと、次に進まないようにしました。次に進んだということは前の工程が完全に終わっていることになりますので、作業する本人、後工程の担当者、管理する側の全員にとっての安心につながります。
またスタッフの中には、まだ経験の少ない人や当社のやり方に慣れていない転職者もいます。部門をまたがる業務の習得は時間がかかるものですが、今はPLMの示す流れに従って仕事をすればスムーズに習得でき、経験の浅い人もすぐに戦力になります」(田畑氏)
もう一つ前川氏が評価するのはワークフローの機能だ。
「以前は紙の書類を持った担当者が、何人もの責任者を回って承認印を得ていましたが、ワークフローなら承認の効率が良くなりますので、納期にも余裕が出てきました。また、承認を得る際に『誰がどういう意見、要望を述べたか』という記録も全体で共有できるという利点もあります」(前川氏)
また一人ひとりの作業も効率化が進んだ。
「PLMシステムには全ての製品情報、部品情報、ドキュメントが掲載されています。どの部品を使うかという部品審議の進捗や、最新の部品単価の確認などもシステム上でできるようになりました。間違って古い価格で計算してしまう不安も解消され、設計と原価管理の担当者はこのシステムを非常に重宝しています」(矢木氏)
稼働後も現場の要望を受けて新機能を次々と開発。新事業への進出も視野に
こうして新PLMが稼働したのだが、PSTはその後も現場からの要望を受け、JSOLと連携して新機能の拡充を継続している。
「以前は業務プロセス上の課題は各自で管理していましたが、新たに課題を登録すると自動的に通知を関連部門に送る機能を追加しました。『課題を提案したのは技術部門だが、対応する部門は品質保証』というようなケースにもスムーズに対応できる環境になりました」(矢木氏)
「新規に設計するときは決められた業務プロセスを全て実行しますが、量産後の変更は一部のプロセスだけを実行します。通常と異なるため漏れや抜けなどに注意が必要となりますが、追加開発した変更起案機能によって、こちらもうまく回せています」(浅野氏)
このように機能拡充の面でも、ものづくリンクの高い拡張性が寄与している。後から必要なモジュールを追加したり開発したりできるので、柔軟に新機能を組み込めるからだ。
「将来的に新たな事業領域・製品領域に乗り出そうとしたときには、その領域に合わせて設計や開発の方法も変えていかざるを得ないでしょうが、今後もJSOLなら我々ユーザー企業の要望や現場の意見を取り入れつつ、使いやすい仕組みを作っていただけると考えています」と田畑氏はJSOLへの期待を述べた。

パワーサプライテクノロジー株式会社 前川 元伸氏、矢木 陽優氏、浅野 公洋氏、田畑 亘氏、
JSOL 松島 寛美、小崎 玄顕
(2023年9月現在)