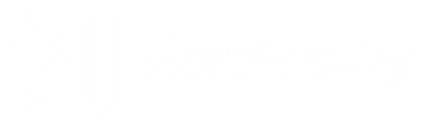複数の自動車メーカーと取引し、ボデーや排気系の部品などの開発、製造に関する事業を国内、海外で展開しているフタバ産業。多くの部門が関わる、量産前の生産準備プロセスでの課題を解決するために、2020 年に導 入を決 定されたのがJSOLの組立製 造業向けPLMソリューション「ものづくリンク」とグループ・グローバル経営管理向け自動化テンプレート「J’sPATTO」だった。
課題
● 以前の生産準備、原価計算のソリューションは、紙での作業をシステム化したことで、転記など非効率な作業が負担だった
● 多くの部門が関わる生産準備プロセスを見直して、業務の効率化と部門間連携を強化し、あるべき姿に近づけたい
解決
● 組立製造業向けPLMソリューション「ものづくリンク」とグループ・グローバル経営管理向け自動化テンプレート「J’sPATTO」の導入
効果
● 2つのソリューションを一体として利用。ものづくリンクにアクセスするだけで、部品表や図面、原価などのデータを利用
● システム刷新にあわせて、各部門の役割を見直し連携を強化
● データモデルの標準化により、新しいデータ活用、DX推進の土台を築く

主査
総務・人事本部
情報システム部 兼
システム企画推進課 課長
武田 博 氏

主査
部品企画統括本部
酒井 幸人 氏
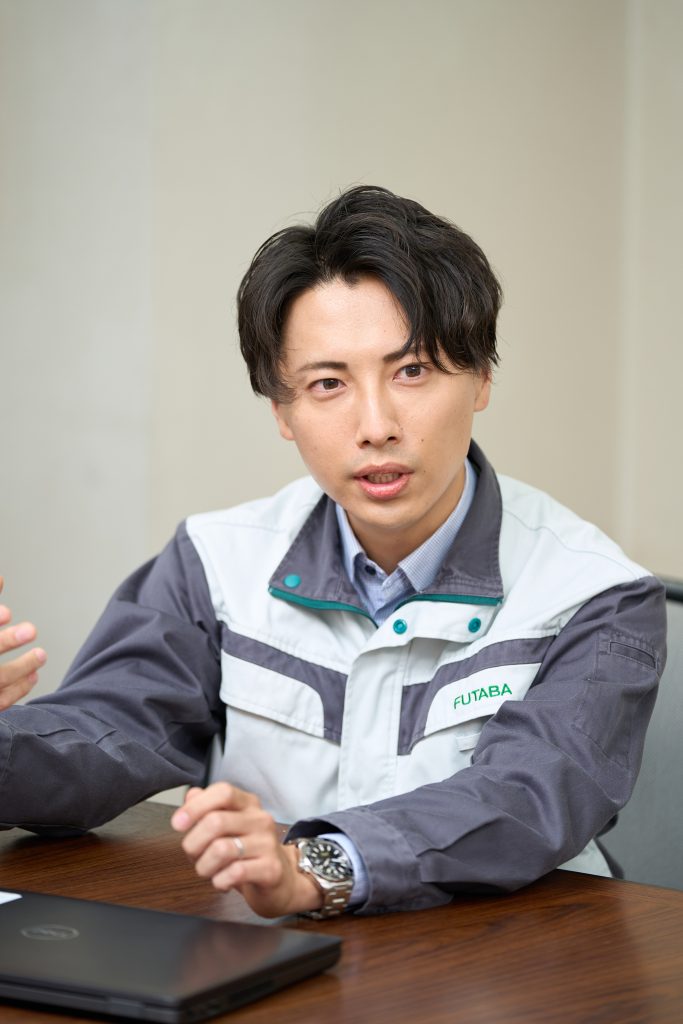
係長
経理・財務本部
原価企画部 排気系部品
近藤 千隼 氏

担当員
部品企画統括本部
ボデー系プロジェクト管理部
ボデー系プロジェクト管理課
長瀬 康成 氏
変化していく自動車業界に対応するために、ダブルSDGsで自ら変革を推進
ボデー系や排気系の自動車部品を主力に、開発から製造まで手掛けているフタバ産業。部品企画統括本部 主査の酒井幸人氏は「複数の自動車メーカーとお付き合いしていくうえで、個々のお客さまの多様なニーズに応え、かつ各社の違いにも対応しながら、提案や開発に織り込んでいく力を強みとしています」と特徴を説明する。
またSDGsに注力している企業は少なくないが、フタバ産業では2つの意味を込めて、「ダブルSDGs」というキーワードを掲げている。
ひとつは一般的な「持続可能な開発目標」だが、もうひとつ は「Solution、Digital、Global」の意味だ。酒井氏は「自動車業界では、EVを始めとする『CASE』と呼ばれる変革が起こっています。当然当社も、変わっていかなくてはいけないという危機感を持ち、会社としてダブルSDGsの視点を持ってDXに取り組んでいます」と姿勢を説明する。
量産前の作業を全面的に見直し、あるべき生産準備の姿を目指す
ものづくりでは量産に移る前に、開発や設計、生産準備のプロセスが行われる。そこでは設計、生産技術、原価計算、購買、品質保証、生産管理などのさまざまな部門が連携を取りながら進められる。かつては紙の指示書を用いてそれらの業務を回していたフタバ産業だったが、2008年にシステム化を実施。それまで月間1,000枚以上の紙の指示書が飛び交っていた現場は、システム化によってペーパーレスとな
り、業務の効率化も格段に進んだ。
だが仕事の進め方そのものは紙の時代を踏襲したものであり、「途中で図面を紙に出力し、それを見ながら再入力する」といった無駄な作業も残っていた。しかし転記が多ければ、作業工程が増えるだけでなく、転記ミスが不具合につながるリスクも生まれる。
また情報伝達が一方通行である点も課題だった。例えば旧システムでは、指示書を送ったあとでどのように対応されたかを知る手段がなく、メールや電話で確認していた。これもまた紙の進め方を踏襲したことによる非効率さだった。
そこで2017年、社をあげて動き出したのが、「開発から生産準備の業務フローを全面的に見直し、業務品質を向上させよう」という取り組みだった。そしてフタバ産業として「あるべき生産準備の形」を模索した結果、導入されたのがJSOLの「ものづくリンク」と「J’sPATTO」だった。ものづくリンクは、部品表を中心とした生産準備に、J’sPATTOは、原価管理に用いられる。
外の世界の長所を取り入れ、競争力強化につながる「生産準備のあるべき姿」を目指して
JSOLを選んだ理由として、総務・人事本部情報システム部 主査 兼 システム企画推進課課長の武田博氏は、当時の状況を「以前のシステムをバージョンアップするという選択肢もありましたが、会社としては『今までと同じことをやっていてはいけない、業務意識を変えていこう』としていた時期でした。また当時のフタバ産業のやり方に対して、『業界標準とは違うのではないか』という疑問を持ち、改善するなら『業界の一般的なやり方、外の世界』を知ったうえで取り組むべきではないかという考えを持っ
ていました」と説明する。
そしてJSOLからの提案に対し、「いくつもの会社に対して生産準備システムを構築したという実績を評価しました。そこで、その実績から得た知見を参考にしつつ、私たちなりの標準化、人材育成、競争力強化につなげていくパートナーとしてJSOLを選んだのです」と続けた。
ものづくリンクの採用が決まったあとにJ’sPATTOも採用されることになるが、そのきっかけとして、JSOLから「これまでの原価計算のやり方は負担が大きい。壮大な転記が行われている」と指摘されたことを、経理・財務本部原価企画部 排気系部品課 係長の近藤千隼氏は挙げた。
原価の扱いについて、フタバ産業では過去に何度かの変遷があった。かつては原価企画部の内部で担当していたが、「各部門が企画、開発段階から原価低減を意識して見積もりを作り、競争力を向上させたい」という考えから、「各部門で見積もりしたものを原価企画部で集約する」という方式に変えた。だが、フタバ産業の見積もり評価項目は非常に緻密であり、集約する際の転記が重い負担となっていたのである。その効率化を実現するために、ものづくリンクとJ’sPATTOを連 携させて活用することが決まった。
「壮大な転記をなくすためにものづくリンクが持つExcel自動読込機能を提案されました。これは各部門が検討した見積もりを自動的に読み込ませてシステムに反映、部品表と一元管理するもので、『まさにこれが欲しかった、私たちの業務にマッチしている』と感じました」(近藤氏)
ものづくリンクとJ’sPATTOが一体として機能。ユーザーはものづくリンクにアクセスすれば、部品表や図面、原価も把握
2022年初、ものづくリンクとJ’sPATTOを連携させた新システムが稼働した。新システムでは、J’sPATTOは 裏 で 稼 働するため、ユーザーはものづくリンクだけを操作すればよいことになる。これにより、部品表を中心にした生産準備プロセスに図面管理、原価管理なども一元管理できるようになり、各部門での連携が進めやすくなった。
ものづくリンクとJ’sPATTOとは双方向でのデータ送受信が可能となっており、ものづくリンクから送られたデータをJ’sPATTOで処理したあとに、ただちにものづくリンクにて参照可能である。さらに、J’sPATTOの計算結果を他のBIツールで分析・参照するというように、他の分析ツールとのやり取りも可能だ。
国内事業だけでなく、グローバル事業での導入効果も大きいと見るのは、部品企画統括本部ボデー系プロジェクト管理部 ボデー系プロジェクト管理課の長瀬康成氏だ。「生産準備指示業務では、グローバル化の対応を強化しました。
以前は日本から海外へという情報発信という一方通行で、海外からの応答は電話やメールを使っていましたが、ものづくリンク上で双方向のやり取りができるようになりました」(長瀬氏)
データモデルの標準化により、将来に向けた新しいデータ活用と人材育成へ
ここまでを振り返り、酒井氏は「2020年にJSOLとタッグを組んで動き始めてから、社内でのデジタル化、その他の取り組みが本当に大きく変わってきました」と感想を述べる。具体的には、RPAやITツール、クラウドツールなどの導入が目立つという。
また今回の刷新では、将来を見据えて活用しやすいようにとデータモデルの標準化にも注力した。ただし、旧システムに蓄積していたデータを新システムに移行する必要があったため、その移行作業は困難を極めた。紙のやり方を踏襲した旧システムのデータの持ち方が独特だったためである。そこで、フタバ産業、JSOL、旧システムのベンダーとの三社が密に連絡を取り合い、慎重にデータ移行を実施した。
「ここ数年で自動車業界はデジタル化が大きく進み、そしてデータの重要性はますます高まりました。機密管理が守れないと生き残れない時代へ移っていく中で、データの持ち方を見直した意味は大きいと思います。当社のやり方、将来の目指す方向にあわせて幾度となく試行錯誤してくれたJSOLには感謝しています」(長瀬氏)
2020年にスタートした今回のプロジェクトは3年目に入るが、今後も数年かけて業務改革を進めていく計画だ。例えば、現時点でも原価企画部での転記作業は旧システムに比べて1/3に削減できたが、近藤氏の視線の先にあるのは「見積もりを自動化し、作業そのものをなくす」ことだ。
「次のステップとしては自動化や基幹システムとのインターフェースの強化、その先にはAIを使った原価の自動算出、売価の自動算出と、年を追うごとにレベルアップしていきたいですね」(近藤氏)
今回の刷新でデータを活用したDX推進への土台ができたという武田氏は「次にやるべきはデジタル人材育成。ものづくリンクにある情報を分析し、新しい問題を解決していく能力を養っていきたい。その面でも、自動車業界や他の業界を含めて、外の世界を知るJSOLには期待している」と述べた。